こんばんは!葉山でございます。
今日はですね
コーチングの歴史について
お話ししたいと思います。
興味ない人もいるかもしれないけど
なぜ生まれたのか?
って歴史を知ることで
スキルの向上につながったりするのと
どうやって進化発展してきたのか?
を知ることによって
コーチングというものへの理解も深まるかなと。
そして、歴史を知ることで
自分のコーチングスタイルや
コーチングマインドも確立されていくので
知るに越したことはないかと。
音楽も同じで
ヴィジュアル系しか知らない人が
オリジナル曲作ったら
どんな楽曲になるか?
想像するの簡単でしょ?
ジャズなんかアウトプットできないわけよw
これがインプットの差ね!
まぁ、これもあたくしの
備忘録的な感じにはなりますが
興味ある人は読んでってね!!
さてさて
コーチの始まりは
15世紀まで遡ります。
「コーチ(Coach)」という
言葉の語源が生まれたのが
15世紀なんですよね〜
中世ヨーロッパの交通の要所で
馬車の産地だったハンガリーの
「コチ」(Kocs地名)に由来してて
そのコチが馬車そのものを指す
名詞になったんだよね
それが「Kocsi(コチ)=馬車」
👉「人を目的地に運ぶ」 という意味が
現代のコーチングの概念に繋がっていくんですね〜。
高級ブランドの
COACHもロゴが馬車ですよね!
Wikiによると…
英語圏では、
目的地まで連れて行ってくれるという類義で
鉄道の客車やバス、運転手付きの自動車も
コーチと呼ばれるようになったんだって!
さらに
教師が鞭を使って教えていた時代の1830年頃
オックスフォード大学の学生間のスラングにおいて
家庭教師が「目的地に連れて行く手段である馬車」
に引っ掛けて「コーチ」と通称したことが由来となり
インストラクターやトレーナー
をも指すようになったとされる。
イギリスではこれが広まり
1861年にはスポーツのトレーナーも
コーチと呼ばれるようになった。
と由来が書いてあるんだけど
ようは、「コーチ=目的地まで運ぶ指導者」
という意味合いだったんだよね。
へ〜〜〜じゃない?
今はコーチ=指導者って解釈じゃないよね?
でも、始まりはそうだったんですね〜。
1861年にスポーツの世界で
コーチ=指導者が生まれたって
背景があるんだけど
どうも調べる限り
ここからコーチの一つの流れが
出来始めている。
この流れが
ティモシー・ガルウェイ(Timothy Gallwey)
「インナーゲーム理論(1974年)」として
世の中に発表されたんだよね。
インナーゲームで提唱されているのが
みんなが知ってるであろう言葉で言うと
「最大の敵は外ではなく、
自分の内なる声(メンタル)」
ってものです。
最大の敵は自分だ!!!
ってよく聞くよね?
あれの始まりが1974年なわけよ!
へ〜〜〜〜じゃない??
さてここで、一つの流れ
と言ったけども
実はコーチングには
元々3つの流れがあって
現代はこの3つの流れが
一つになり
コーチングという業界になってるって感じ。
(あくまで葉山調べね)
一つがこの
スポーツから生まれたもの
メンタル・能力開発とか
一つが
心理学や精神分析から生まれたもの
自己理解・潜在意識とか
一つが
ビジネスシーンで生まれたもの
リーダシップとか目標達成とかね
大きくこの3つの流れになってる。
では、話を戻して
ティモシー・ガルウェイ(Timothy Gallwey)
彼は元々テニスコーチで
あらゆるスポーツに応用できる
インナーゲーム=
(心の中にいるセルフ1とセルフ2のゲーム)
を解説したわけです。
セルフ1というのが
心の中で指示をしている自分
セルフトークの自分ね
セルフ2というのが
実際に動いたり行動している自分
このセルフ1とセルフ2の
関係性が良ければ
いいパフォーマンスを発揮するけど
大体仲悪いよね?って話
基本的に
セルフ1の自分が
セルフ2の自分を
責めまくってるわけですよ
「何でミスしたんだ!」
「この前も同じ失敗をしたじゃないか!」
「何で出来ないんだ!」
こんな感じ。
さらに
指導者からの声は
セルフ1と同じ役割があるから
「もっとこうしろ!」
「今手の返しが甘かった!」
「反応するのが遅い!」
「もっと相手の動きを見ろ!」
と指示をすればするほど
プレイヤーのパフォーマンスは
落ちていくことに気づいて
《何も言わず観察する》
と、パフォーマンスが上がっていった
って話なんですよ。
つまり、パフォーマンスを上げるためには
セルフ1を黙らせて
もっと感覚的にパフォーマンスをしろ!
みたいな、そんな概念なんですね。
そのためには〜〜
と続くのですが
興味のある方は
インナーゲームを読んでみるのも
いいかもしれませんね!
さて、このインナーゲーム理論
現代のコーチングにも応用されてますよね
それが、
・セルフトーク(自己対話)のコントロール
・自分をジャッジしない
・マインドフルネス(雑念除去)
頭で考えすに動こうとかも
動きたくなる自分を解放するとかも
この理論がベースになってる。
そうすることで
フロー状態になって
今この瞬間に全ての集中させられている
ってことね!
全集中ですよ。
トーーーンタンタンですよ。
このフロー状態ってのを提唱したのが
心理学者ミハイ・チクセントミハイです。
フロー状態とは心理学で
「時間が経つのを忘れるほど作業に没頭し、
他のことが気にならなくなるような状態」
のことを指します。
このフローという概念
1970年代に提唱してるんですよね〜
はい、きました。
心理学とスポーツが
混じり合いましたね〜
ミハイ・チクセントミハイは
ポジティブ心理学の父
とも呼ばれていて
第二次世界大戦後
荒廃した祖国ハンガリーで
人々が生きる希望を失う姿を
目の当たりにした経験から
「生きる意味」と「幸福とは何か」と
いう問いを持ち続け
シカゴ大学で幸福感についての
研究をはじめた人です。
もう、名前覚えられない…
チルチルミチルにしか見えない、、、
このように1970年代に
スポーツの世界で提唱されていることと
心理学で提唱されていることが
融合することによって
さらにコーチングによる効果が
心理学的にも効果的だと
言われるようになったんですね。
ここで出ました心理学
コーチングを語る上で
外せない学問ですね。
当時の心理学とは
どういったものだったのか?
この深掘りをまた明日お届けしますね!
んじゃ🖐️

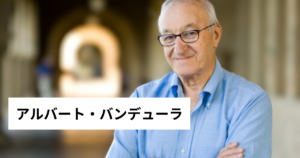

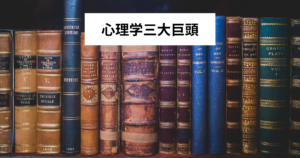


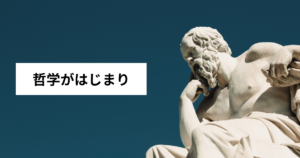
コメント